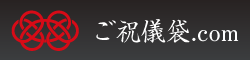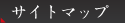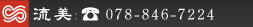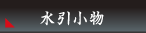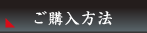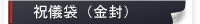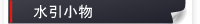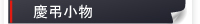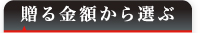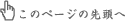HOME > 水引の歴史
水引の歴史
水引の由来

水引の由来は、今からはるか約1400年前の飛鳥時代にさかのぼります。遣隋使・小野妹子が帰朝した際、隋からの使者が携えてきた贈り物に紅白に染められた麻紐が結ばれていました。これは海路の安全を祈願してつけられたものでしたが、そのまま宮廷に献上したところ大変喜ばれたのです。それ以来、宮廷への献上品には、紅白の麻布を結ぶことが慣例となりました。
水引の発展

平安時代にはこの紅白の麻紐を「くれない」と呼ぶようになりました。やがて和紙が発明されると、水引にも紙紐が使われるようになりました。
一説によると、「水引」という名前は和紙をよりあわせてこより状にし、それに水のりを引いて乾かすという作り方からきているともいわれています。しかし、当時はまだ和紙が高級品だったため、一般の人々には広まるにはいたりませんでした。
水引の普及

江戸時代になると庶民の生活の中にも水引が定着し、全国へと徐々に普及していきました。さらに大正から昭和にかけて機械化による大量生産が始まると、装飾品など幅広い用途に使われるようになりました。現在では、信州飯田(長野県)と伊予三島・川之江(愛媛県)が全国の二大生産地として有名です。